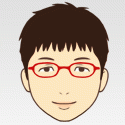CFJ訴訟 被告の準備書面(1)
こちらの請求は、
過払い金(約6.7万円)+5%利息(約2.7万円)+訴訟費用。
第1回口頭弁論後に、CFJから連絡があり、
こちらからは、103,000円(訴訟費用込み)を提示。
第2回口頭弁論当日に、裁判所で答弁書を受け取る。
(準備書面は3/19 14:00頃、裁判所にFAXされたもの。)
↓↓↓↓↓↓ ここから 被告の準備書面(1) ↓↓↓↓↓↓
前記当事者間の御庁頭書事件につき、被告は早期の和解を希望し、答弁書にて和解案を提示したが、原告との間で和解が成立しなかったため、改めて本件係争に関して被告の主張を行う。答弁書にて、請求の原因に対する答弁・認否を行っているが、留保した部分も含めて、より詳しく反論するため、下記にて、請求の原因に対する答弁・認否から被告主張を行う。
第1.請求の原因に対する答弁・認否
1、第1項については、認める。
2、第2項ないし第5項については、次のとおりである。
①原被告間に、甲第1号証(取引明細書)で示される金銭消費貸借取引(以下、「本件取引」という。)で管理される金銭消費貸借取引を原因とする債権債務が存在することは認める。
②原告が示した甲第2号証について、各回取引における取引年月日、借入金額、返済金額は認めるが、被告を悪意の受益者とする利息が発生都度付加されている点は否認もしくは争う。
③被告が悪意の受益者であるとの原告主張を否認する。
平成21年1月22日に為された最高裁判決により、過払い金が発生する都度利息が発生し後の貸付金に充当されるとの原告主張は排斥されるべきで、これについて後に詳述する。
④その余については否認もしくは争う。
第2.被告に過払利息の返還義務が存在しないこと
1、はじめに
原告は、被告が「悪意の受益者」(民法704条)、すなわち、「法律上の原因のないことを知りながら利得をした者」(最高裁昭和37年6月19日判決、裁判集61号251頁)に該当すると主張し、過払金発生時から過払利息(年5分)を付加した請求を行っている。
しかしながら、最高裁平成21年1月22日判決(同庁20年(受)第468号、以下、「平成21年1月判決」という。)を前提とすると、少なくとも継続的な金銭消費貸借取引が終了するまでは、被告は、過払利息(年5分)の返還義務を負担しない。
また、最高裁平成19年7月13日判決(同庁平成18年(受)第276号、以下、「平成19年7月判決」という。)が示した基準に従えば、被告は「悪意の受益者」(民法704条)に該当せず、過払利息(年5分)の返還義務を負担する余地はない。
以下、詳述する。
2、平成21年1月判決の判示内容からの考察
(1)民法704条の趣旨
悪意の受益者に利息返還義務を課す民法704条の趣旨は、不当利得者に通常かつ最小限の損害賠償をされる点にある(福地俊雄「新版注釈民法(18)」、655頁)。そして、悪意の受益者にのみこの損害賠償義務を課した背景には、「不当利得返還債務は、法倫理的観点を土台においてみれば、利得者がそれを自覚(悪意)したならば直ちに返還すべき債務(同648頁)」であるとの事情がある。
(2)平成21年1月判決の趣旨(不確定期限の合意)
他方、平成21年1月判決によれば、「過払金充当合意」には、「基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借が終了した時点で過払金が存在していればその返還請求権を行使することとし、それまでは過払金が発生してもその都度その返還を請求することはせず、それをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨」(以下この「趣旨」を「不行使の合意」という。)が含まれており、この「不行使の合意」を含む過払金充当合意が不当利得返還請求権行使の法律上の障害となるという。最も一般的にみられる法律上の障害は弁済期の定めであるから(川島武宜「注釈民法(5)」282頁)、本件においても、「不行使の合意」とは、「不当利得返還請求権の弁済期について、取引最終時という不確定期限を付す合意」であると解するのが相当である。
この点、他の解釈によっては法の枠組みの中で整合的に説明することができない。まず、時効の利益をあらかじめ放棄することは許されない以上(民法146条)、不行使の合意は、あらかじめ時効を進行させないとの当事者間の合意ではあり得ない。
また、法律上の障害であっても、債権者側の意思によって除くことができる場合には時効を停めないと解されている(川島武宜「注釈民法(5)」282頁)以上、債権者の意思で過払金返還請求権は法定債権である不当利得返還請求権であり、当事者間の契約に基づいて形成される契約上の権利ではないから、当事者間の合意から権利の内容を解釈して、法律上の障害たる「権利そのものの性質上内在する障害」(川島武宜「注釈民法(5)」282頁)が存在すると認定することもできないのである。
(3)弁済期未到来の過払金返還請求権の利息は発生しない
このように、「過払金充当合意」のある消費貸借取引においては、貸主が不当利得返還債務を負い、かつ仮に悪意と認定されたとしても、弁済期が未到来であるから「直ちに返還すべき」債務ではない。したがって、利息返還義務を課した民法704条が想定する前提、すなわち「直ちに返還すべき」不当利得が存在する状況とは事情を異にし、悪意の受益者に損害賠償責任を負わせるべき根拠を欠く。
また、かかる損害賠償責任の法的性質につき、いわゆる不法行為責任説を採っても、法定責任あるいは不法行為的責任説を採っても(福地俊雄「新版注釈民法(18)」、657頁参照)、いずれにせよ賠償責任発生の根拠は、利得を保有することに何らかの不法性ないし不当性が存在することにある。しかるに過払金充当合意が存在する場合、貸主は借主との合意に基づいて、新しい貸付があればいつでも充当できるように、借主のために過払金を保有しているのだから、もはや損害賠償責任発生の根拠となる不法性も不当性も失われている。
さらに、「過払金充当合意」をした当事者の意思としても、貸主の利息返還義務は生じないことを前提としていたものと認められる。借主は、過払金を貸主に保持させて簡便な消費貸借取引を継続する代わりに、返還請求によって過払金を取り戻す利益を放棄したのであるから、過払金からの利息収入についても放棄したものと認めるのが当事者の合理的意思解釈として相当であり、借主の得べかりし利益としての「損害」を想定することはできない。平成21年1月判決が過払金を「そのまま」その後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するとのべているのも、利息を付することなく過払金元本を「そのまま」充当するとの判示と考えられる。
したがって、少なくとも「過払金充当合意」が継続している取引終了時までは、被告に過払利息(年5分)の返還義務は存在しないのである。
(4)なお、この結論は、平成21年1月判決の想定する典型的な事実関係になじむものである。すなわち、平成21年1月判決は「金銭消費者貸借契約が終了した時点で過払金が存在していればその返還請求権を行使する」と判示しているとこと、これによれば、「不行使の合意」による制限がある不当利得返還請求権が、行使可能な権利として現実化するのは、「金銭消費貸借契約が終了した時点で過払金が存在」しているときだけである。つまり、「不行使の合意」により、不当利得返還請求権は、取引終了までの間、行使不可能な権利として存在しており、後の借入金債務への充当の有無、時期、金額等によってその内容が変動する不確定な権利となっている。そうすると、不当利得返還請求権を行為して借主が返還を求めるべき利益も、「金銭消費貸借契約が終了した時点」でしか確定されない。
したがって、貸主は、継続的な消費貸借契約により受けた利益が確定する取引終了時において、はじめて過払利息(年5分)の返還義務を負担すると解するのが、当事者間の取引実態にも合致しているのである。
この点、大阪高裁平成20年4月18日判決(同庁平成19年(ネ)第3343号、乙第1号証)も、「過払金充当合意」の存在を認定した上で、「・・・したがって、本件において、過払金の不当利得返還請求権の金額や内容は、後の貸付への充当が行われないこととなる取引終了日以降に確定するのであり、当該時点までは金額や内容が不確定、不動的であって、後の貸付への充当の有無、充当額等により変動することが予測されるから、利得の金額や内容も不確定、不動的であり、これにつき利息を付して返還させることは、当該利息の金額や内容自体不確定、不動的である上、不当利得制度を支える公平の原理をも考慮すると、不相当である。」と判示し、過払利息が発生し得るのは取引終了時以降であるとしている。
そして、上記大阪最高裁判決を不服とした上告受理申立につき、最高裁平成21年1月22日決定(同庁平成20年(受)第1317号、乙第2号証)は、裁判官全員一致の意見で、不受理の決定を行っている。
また、上記平成21年1月判決を踏襲し、過払利息が発生し得るのは取引終了時以降であるとの裁判例が続いている(乙第3号証)。
3、平成19年7月判決の判示内容からの考察
(1)平成19年7月判決は、「貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められないときは、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる特段の事情がある場合でない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得したもの、すなわち民法704条の『悪意の受益者』であると推定されるものというべきである。」と判示する。
したがって、仮に、みなし弁済が成立しない場合でも、被告が、「貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる特段の事情」が存在すれば、「悪意の受益者」(民法704条)に該当しないので、過払利息(年5分)の返還義務を負わないものと解する。
以下、「上記認識の有無」及び「特段の事情の有無」につき、検討する。
(2)「上記認識の有無」について
ア. みなし弁済の成立要件は、①貸主が「登録業者」であること、②貸主が貸付を行う際に、「17条書面を交付」していること、③貸主が弁済を受ける際に、「18条書面を交付」していること、④借主が制限超過利息を「任意に弁済」したこと、である(貸金業法43条1項)。
イ. 本件では、まず、被告(関東財務局長(4)第01265号)及び被告の前身であるディックファイナンス株式会社(近畿財務局長(1)第00671号)が「登録業者」である点につき、問題はない。
ウ. 次に、被告及び被告の前身であるディックファイナンス株式会社(以下、「ディック」という。)の極度額借入契約書兼告知書のサンプル(乙第4号証の1・2)には、貸主の名称(商号)、所在地、登録番号、契約年月日、契約番号、利率、返済方式、返済期間・回数、遅延損害金の割合、融資限度額等が記載され、また、領収証兼ご利用利用明細票のサンプル(乙第5号証の1・2)にも、上記極度額借入契約書兼告知書と同様の事項が記載されているので、被告及びディックが貸付を行う際に、旧貸金業規制法17条1項及び同施行規則13条に定める事項を記載した「17条書面を交付」していたことは明白である。
エ. 更に、上記ウで主張立証した通り、被告及びディックの領収証兼ご利用明細票のサンプル(乙第6号証の1・2)には、貸主の名称(商号)、所在地、登録番号、契約年月日、契約番号、利率、返済方式、返済期間・回数、遅延損害金の割合、融資限度額等が記載されているので、被告及びディックが弁済を受ける際に、旧貸金業規制法18条及び同施行規則15条に定める事項を記載した「18条書面を交付」していたことは明白である
オ. 最後に、「債務者が利息として任意に支払った」(貸金業法43条1項)とは、「債務者が利息の契約に基づく支払に充当されることを認識した上、自己の自由な意思によって支払ったことをいい、債務者において、その支払った金銭の額が利息の制限を越えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しないと解するのが相当である(最高裁昭和62年(オ)第1531号平成2年1月22日第二小法廷判決・民集44巻1号332頁参照。)。」とされるので、当事者間の合意に基づく原告の支払いは、強制執行、貸主等の威迫等(貸金業法21条)に起因するものでない限り、「任意の弁済」であることが明白である。
カ. 以上により、被告が貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有していたことは肯定できる。
(3)「特段の事情の有無」について
ア. 上記(2)で主張立証した通り、被告が、貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有していたことは肯定できるので、「そのような認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる特段の事情」が存在すれば「悪意の受益者」(民法704条)には該当しない。
イ. この点、被告では、みなし弁済の成否によって営業利益が大きく左右されるので、それが成立するためのシステム(みなし弁済システム)を長年にわたって構築・整備してきた。その結果、熊本地裁平成13年4月20日判決(同庁平成12年(レ)第25号)などでは、被控訴人(一審被告)のみなし弁済の抗弁が採用され、控訴人(一審原告)の控訴は棄却されている。
にもかかわらず、みなし弁済の成立が否定されるに至ったのは、みなし弁済の成立要件に関する解釈に変更が生じたことが原因であり、以下で詳細する通り、「被告の努力によっては如何ともしえない外部的な要因に起因」するものである。
ウ. 要件解釈の変遷
(ア)平成16年2月20日最高裁判決まで
当初は、任意性要件及び第17条・第18条書面要件について、いわゆる緩和説を採用する最高裁判決が存在し、当時の下級審判例及び学説も緩和説を採用するものが見られた。すなわち、最高裁平成2年1月22日判決(民集44巻1号332頁)は、みなし弁済における「任意」とは、債務者が利息の契約に基づく利息または賠償額の予定に基づく賠償金の支払いに充当されることを認識した上、自己の自由な意思によって支払ったことをいい、支払い金額が利息制限法の制限を超過していたことや、当該超過部分の契約が無効であることまでの認識は不要とし、任意性要件を緩やかに解していた。そして、この事件で、上告人は①契約年月日の記載が真実と異なる②借り換えの場合に記載すべき旧債務の金額が記載されていない と主張したが、最高裁はいずれも第17条書面の欠陥として取り上げず、みなし弁済を認めた。また、同判決の判例評釈(ジュリ959号92頁)において、当時最高裁調査官であった滝澤孝臣氏は、第17条及び第18条書面について、「契約書面及び受取証書の記載事項が法一七条及び一八条の所定事項、さらに大蔵省令の所定事項、銀行局長通達の所定事項のすべてを網羅していること、またその記載事項が事実と寸分違わず一致していることを要するというような杓子定規な解釈適用ではなく、事実に即した幅のある弾力的な解釈適用を肯認する趣旨に解される」と述べており、第17条・第18条書面要件についても、この当時、最高裁はいわゆる緩和説を採用していたものと考えられる。
その後の判例、学説等を見ても、さまざまな見解が錯綜し、統一が図られていなかった。確かに、第17条・第18条書面要件について、わずかな記載漏れも許されないとする下級審の裁判例も存在する一方、書面用件の不備ないし欠陥によって債務者が不利益を被るか否かを実質的に判断し、結果として要件を満たす旨判断した裁判例も複数存在し(東京高裁平成9年6月10日判決(判夕966号243頁)、最高裁平成11年3月11日判決(民集53巻3号451頁)、福岡地裁平成12年1月28日判決(金判1088号47頁)、名古屋高裁平成13年7月12日判決(判夕1126号280頁)、札幌高裁平成14年2月28日判決(金判1142号23頁)等)、また、第17条・第18条書面要件の解釈については、消費者金融の実務に照らして弾力的かつ緩やかな解釈を行うべきであるとする学説も有力に展開されていた(例えば、遠藤美光「貸金業規制法43条1項における書面の要件」ジュリ987号109頁、吉野正三郎「貸金業規制法17条の書面要件について」ジュリ1212号64号等)。
任意性要件についても、緩和説を採用した上記最高裁平成2年1月22日判決を前提に、期限の利益損失条項が含まれる金銭消費貸借契約に基づく制限超過利息の支払について、任意性を否定した判例は、ただの一つも存在しなかった。最近公表された前述の滝澤孝臣氏の論稿(銀行法務21・659号4頁)においても、同最高裁平成2年1月22日判決以降の状況に関して、「平成2年判決が言い渡されてから現在まで多数の貸金業取引関係訴訟が係属したなかで、かつ、貸金業取引のほとんどに期限の利益喪失約款が存在するのではないかと窺われるので、期限の利益喪失約款の下での利息ないし損害金の支払いの任意性といった法律問題は、みなし弁済規定の適否が争われる事案では、法律の適用として、裁判所で当然に問題となっていた事項であると解されるなかで、これまでに支払いの任意性が否定されるとの裁判例」がなかった旨述べられているところである(同13頁)、また、大蔵省の外郭団体が出版している解説書である「新訂実例問答集 貸金業法のすべて」(財団法人大蔵財務協会編 平成10年)においては、「任意」の意味について「一般に詐欺、錯誤、強迫が認められ、又は強制執行によって強制的に弁済にあてられた場合を除くものと解されており、規制法43条の『任意』もこれと変わることはないものと解される」とし(同220頁)、任意性が否定される場合を「詐欺」「錯誤」「強迫」「強制執行」といった例外的な場合に限定し、一般の意味にしたがって任意性を認める考えを示していた。
(イ)平成16年2月20日最高裁判決以降
しかし、最高裁は、平成16年2月20日判決において、「法43条1項の規定の適用要件については、これを厳格に解釈すべきもの」とし、第17条・第18条書面要件について、緩和説を捨て去り、厳格説を採用したようなことを述べるに至った。
他方、下級審においては混乱が続き、たとえば福岡高裁平成16年11月18日判決(平成16年(ネ)第488号、公刊物未搭載)は、「返済期間及び返済回数(貸金業法17条1項6頁)の記載を要しないと解すべきであるし、そのように解しても、債務者の保護に欠けることはないというべきである」として、いわゆるリボルビング取引についてみなし弁済の成立を認めた。
また、最高裁自身も、平成17年12月15日、厳格説に立ちつつも、その解釈に一定の幅を認める注目すべき判決を下している(消費者法ニュース・66号36頁)。すなわち、第17条書面の要件について、貸付契約の性質上、法定記載事項のうち、確定的な記載が不可能な事項があった場合、当該事項の記載の義務を免れるものではないとしつつも、当該事項に「準じた事項」を記載すれば、当該事項を記載したものと解すべき旨判示しているのである。つまり、最高裁も、厳格説に立ちつつも、貸金業者に不可能を強いることまでは否定し、契約の性質からして可能な限りの法定記載事項に「準じた記載」をすれば、第17条書面の要件を満たすものと認めているのである。これは第17条書面の要件を厳格に解釈しつつも絶対視せず、契約の性質に応じた被告の合理的な努力を評価するものといえる。したがって、厳格説といっても、それは全ての場合において、第17条・第18条書面要件として法文上定められている事項が厳格に一言一句反映されていることまでを要求するものではなく、契約の性質に応じた柔軟な解釈の余地を残すものというべきである。
さらに、任意性要件については、前記の最高裁平成16年2月20日判決は直接判示しておらず、その後の東京高裁平成16年12月21日判決(金判1208号13頁)においては、緩和説を採用する従前の最高裁平成2年1月22日判決を前提に、期限の利益損失特約の存在によって直ちに制限超過利息の支払が強制されることはないとし、前述した滝澤孝臣判事も同東京高裁判決を支持していた(金判1231号11頁)。
(ウ)平成18年1月13日最高裁判決以降
ところが、最高裁は、その後厳格な立場を強め、平成18年1月13日判決において、第18条書面の記載事項の一部省略を認める貸金業規制法施行規則第15条2項の規定の一部を無効とし、さらに、同判決、同月19日判決(裁時1404号71頁)及び同月24日判決(裁時1404号89頁)において、金銭消費貸借に制限超過利息の支払を遅滞した場合の期限の利益損失条項がある場合には、特段の事情がない限り、支払いの任意性が否定されるとの判断を下したことは周知のとおりである。
エ. 結論
以上のとおり、みなし弁済の成立が否定されるに至ったのは「みなし弁済の成立要件に関する解釈に変更が生じたことが原因であり、被告の努力によっては如何ともしえない外部的な要因に起因」するものである。
そして、上記事情に加えて、「通説は現実に知る者だけが悪意の受益者であり、善意であれば、過失の有無を問わず、前条の責任のみを負うものとする。」(「新版注釈法(18)」、640頁)と理解していること、及び「ある利得が将来法律上の原因を欠くものとなる可能性を知る場合については、・・・一般的には、そのような場合は必ずしも悪意の受益者とはいえない。」(「新版注釈法(18)」、641頁)と解されていることに鑑みれば、本件には、「みなし弁済が成立するとの認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる特段の事情」が存在するので、被告は、「悪意の受益者」(民法704条)には該当しない。
4、総括
以上の被告の主張を総括すれば、そもそも被告は「悪意の受益者」(民法704条)に該当しないので、過払利息(年5分)の返還義務を負わないし、仮に、「悪意の受益者」(民法704条)に該当する場合でも、過払金の不当利得返還請求権の金額や内容は、継続的な金銭消費貸借取引終了日以降に確定するものであって、当該時点までは金額や内容が不確定、不動的であるから、過払金の不当利得返還請求権の金額や内容、その権利が確定した日、すなわち、原告の当該返還請求権の行使により被告がその訴状を受領した日の翌日までは、過払利息(年5分)の返還義務を負わないもとの解する。
5、本件で被告が原告に負う不当利得返還債務の金額
上記主張にて、被告が原告に負う不当利得返還債務は、以下の金額を越えて存在しない。
・本件取引 金66,897円(被告別紙計算書)
第3.和解提案
(1)はじめに
被告は、原告との本件争いについて和解による解決を希望しており、被告は答弁書にて6万円の和解案を提示したが、原告は「印紙1,000円、郵券4,000円、資格証明1,000円、訴状作成費用1,000円及び、支払日迄5%でないと和解しない」と判決と同様の内容であった為、合意に至っておりません。
和解とは、『当事者間に存在する法律関係の争いについて、当事者が互いに譲歩し、争いを止める合意をすることをいう。和解契約が成立するためには、以下の要件を満たすことが必要である(民法695条)。①当事者間に争いが存在すること、②当事者が互いに譲歩すること、③争いを解決する合意をすること(出典:フリー百科事典ウィキペディア(Wikipedia))。』である。
被告は、本件について早期の解決を希望するものであり、当事者が互いに譲歩し、和解に応じて頂けたらと思います。
原告におかれましては、このあたりを勘案して和解に応じて頂きたいと願います。もしくは、裁判所による和解勧告の実施を希望いたします。
(2)和解案
被告は、原告との本件争いについて和解による解決を希望する。答弁書にて6万円の和解案を提示したが、原告との間で和解が成立しなかったため、改めて本件係争に関して和解案を提示する。被告は、原告に対し、本件解決金として金75,000円を上限に、5月22日を支払日として支払う用意がある。
第4.被告の主張・要望
1.被告は、続行期日に欠席した場合、本書面の内容を擬制陳述いたします。
2.被告は、本件訴訟の速やかな解決のため、和解勧告を出して欲しい為、上申いたします。
↑↑↑↑↑↑ ここまで 被告の準備書面(1) ↑↑↑↑↑↑
過払い金(約6.7万円)+5%利息(約2.7万円)+訴訟費用。
第1回口頭弁論後に、CFJから連絡があり、
こちらからは、103,000円(訴訟費用込み)を提示。
第2回口頭弁論当日に、裁判所で答弁書を受け取る。
(準備書面は3/19 14:00頃、裁判所にFAXされたもの。)
↓↓↓↓↓↓ ここから 被告の準備書面(1) ↓↓↓↓↓↓
前記当事者間の御庁頭書事件につき、被告は早期の和解を希望し、答弁書にて和解案を提示したが、原告との間で和解が成立しなかったため、改めて本件係争に関して被告の主張を行う。答弁書にて、請求の原因に対する答弁・認否を行っているが、留保した部分も含めて、より詳しく反論するため、下記にて、請求の原因に対する答弁・認否から被告主張を行う。
第1.請求の原因に対する答弁・認否
1、第1項については、認める。
2、第2項ないし第5項については、次のとおりである。
①原被告間に、甲第1号証(取引明細書)で示される金銭消費貸借取引(以下、「本件取引」という。)で管理される金銭消費貸借取引を原因とする債権債務が存在することは認める。
②原告が示した甲第2号証について、各回取引における取引年月日、借入金額、返済金額は認めるが、被告を悪意の受益者とする利息が発生都度付加されている点は否認もしくは争う。
③被告が悪意の受益者であるとの原告主張を否認する。
平成21年1月22日に為された最高裁判決により、過払い金が発生する都度利息が発生し後の貸付金に充当されるとの原告主張は排斥されるべきで、これについて後に詳述する。
④その余については否認もしくは争う。
第2.被告に過払利息の返還義務が存在しないこと
1、はじめに
原告は、被告が「悪意の受益者」(民法704条)、すなわち、「法律上の原因のないことを知りながら利得をした者」(最高裁昭和37年6月19日判決、裁判集61号251頁)に該当すると主張し、過払金発生時から過払利息(年5分)を付加した請求を行っている。
しかしながら、最高裁平成21年1月22日判決(同庁20年(受)第468号、以下、「平成21年1月判決」という。)を前提とすると、少なくとも継続的な金銭消費貸借取引が終了するまでは、被告は、過払利息(年5分)の返還義務を負担しない。
また、最高裁平成19年7月13日判決(同庁平成18年(受)第276号、以下、「平成19年7月判決」という。)が示した基準に従えば、被告は「悪意の受益者」(民法704条)に該当せず、過払利息(年5分)の返還義務を負担する余地はない。
以下、詳述する。
2、平成21年1月判決の判示内容からの考察
(1)民法704条の趣旨
悪意の受益者に利息返還義務を課す民法704条の趣旨は、不当利得者に通常かつ最小限の損害賠償をされる点にある(福地俊雄「新版注釈民法(18)」、655頁)。そして、悪意の受益者にのみこの損害賠償義務を課した背景には、「不当利得返還債務は、法倫理的観点を土台においてみれば、利得者がそれを自覚(悪意)したならば直ちに返還すべき債務(同648頁)」であるとの事情がある。
(2)平成21年1月判決の趣旨(不確定期限の合意)
他方、平成21年1月判決によれば、「過払金充当合意」には、「基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借が終了した時点で過払金が存在していればその返還請求権を行使することとし、それまでは過払金が発生してもその都度その返還を請求することはせず、それをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨」(以下この「趣旨」を「不行使の合意」という。)が含まれており、この「不行使の合意」を含む過払金充当合意が不当利得返還請求権行使の法律上の障害となるという。最も一般的にみられる法律上の障害は弁済期の定めであるから(川島武宜「注釈民法(5)」282頁)、本件においても、「不行使の合意」とは、「不当利得返還請求権の弁済期について、取引最終時という不確定期限を付す合意」であると解するのが相当である。
この点、他の解釈によっては法の枠組みの中で整合的に説明することができない。まず、時効の利益をあらかじめ放棄することは許されない以上(民法146条)、不行使の合意は、あらかじめ時効を進行させないとの当事者間の合意ではあり得ない。
また、法律上の障害であっても、債権者側の意思によって除くことができる場合には時効を停めないと解されている(川島武宜「注釈民法(5)」282頁)以上、債権者の意思で過払金返還請求権は法定債権である不当利得返還請求権であり、当事者間の契約に基づいて形成される契約上の権利ではないから、当事者間の合意から権利の内容を解釈して、法律上の障害たる「権利そのものの性質上内在する障害」(川島武宜「注釈民法(5)」282頁)が存在すると認定することもできないのである。
(3)弁済期未到来の過払金返還請求権の利息は発生しない
このように、「過払金充当合意」のある消費貸借取引においては、貸主が不当利得返還債務を負い、かつ仮に悪意と認定されたとしても、弁済期が未到来であるから「直ちに返還すべき」債務ではない。したがって、利息返還義務を課した民法704条が想定する前提、すなわち「直ちに返還すべき」不当利得が存在する状況とは事情を異にし、悪意の受益者に損害賠償責任を負わせるべき根拠を欠く。
また、かかる損害賠償責任の法的性質につき、いわゆる不法行為責任説を採っても、法定責任あるいは不法行為的責任説を採っても(福地俊雄「新版注釈民法(18)」、657頁参照)、いずれにせよ賠償責任発生の根拠は、利得を保有することに何らかの不法性ないし不当性が存在することにある。しかるに過払金充当合意が存在する場合、貸主は借主との合意に基づいて、新しい貸付があればいつでも充当できるように、借主のために過払金を保有しているのだから、もはや損害賠償責任発生の根拠となる不法性も不当性も失われている。
さらに、「過払金充当合意」をした当事者の意思としても、貸主の利息返還義務は生じないことを前提としていたものと認められる。借主は、過払金を貸主に保持させて簡便な消費貸借取引を継続する代わりに、返還請求によって過払金を取り戻す利益を放棄したのであるから、過払金からの利息収入についても放棄したものと認めるのが当事者の合理的意思解釈として相当であり、借主の得べかりし利益としての「損害」を想定することはできない。平成21年1月判決が過払金を「そのまま」その後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するとのべているのも、利息を付することなく過払金元本を「そのまま」充当するとの判示と考えられる。
したがって、少なくとも「過払金充当合意」が継続している取引終了時までは、被告に過払利息(年5分)の返還義務は存在しないのである。
(4)なお、この結論は、平成21年1月判決の想定する典型的な事実関係になじむものである。すなわち、平成21年1月判決は「金銭消費者貸借契約が終了した時点で過払金が存在していればその返還請求権を行使する」と判示しているとこと、これによれば、「不行使の合意」による制限がある不当利得返還請求権が、行使可能な権利として現実化するのは、「金銭消費貸借契約が終了した時点で過払金が存在」しているときだけである。つまり、「不行使の合意」により、不当利得返還請求権は、取引終了までの間、行使不可能な権利として存在しており、後の借入金債務への充当の有無、時期、金額等によってその内容が変動する不確定な権利となっている。そうすると、不当利得返還請求権を行為して借主が返還を求めるべき利益も、「金銭消費貸借契約が終了した時点」でしか確定されない。
したがって、貸主は、継続的な消費貸借契約により受けた利益が確定する取引終了時において、はじめて過払利息(年5分)の返還義務を負担すると解するのが、当事者間の取引実態にも合致しているのである。
この点、大阪高裁平成20年4月18日判決(同庁平成19年(ネ)第3343号、乙第1号証)も、「過払金充当合意」の存在を認定した上で、「・・・したがって、本件において、過払金の不当利得返還請求権の金額や内容は、後の貸付への充当が行われないこととなる取引終了日以降に確定するのであり、当該時点までは金額や内容が不確定、不動的であって、後の貸付への充当の有無、充当額等により変動することが予測されるから、利得の金額や内容も不確定、不動的であり、これにつき利息を付して返還させることは、当該利息の金額や内容自体不確定、不動的である上、不当利得制度を支える公平の原理をも考慮すると、不相当である。」と判示し、過払利息が発生し得るのは取引終了時以降であるとしている。
そして、上記大阪最高裁判決を不服とした上告受理申立につき、最高裁平成21年1月22日決定(同庁平成20年(受)第1317号、乙第2号証)は、裁判官全員一致の意見で、不受理の決定を行っている。
また、上記平成21年1月判決を踏襲し、過払利息が発生し得るのは取引終了時以降であるとの裁判例が続いている(乙第3号証)。
3、平成19年7月判決の判示内容からの考察
(1)平成19年7月判決は、「貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められないときは、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる特段の事情がある場合でない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得したもの、すなわち民法704条の『悪意の受益者』であると推定されるものというべきである。」と判示する。
したがって、仮に、みなし弁済が成立しない場合でも、被告が、「貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる特段の事情」が存在すれば、「悪意の受益者」(民法704条)に該当しないので、過払利息(年5分)の返還義務を負わないものと解する。
以下、「上記認識の有無」及び「特段の事情の有無」につき、検討する。
(2)「上記認識の有無」について
ア. みなし弁済の成立要件は、①貸主が「登録業者」であること、②貸主が貸付を行う際に、「17条書面を交付」していること、③貸主が弁済を受ける際に、「18条書面を交付」していること、④借主が制限超過利息を「任意に弁済」したこと、である(貸金業法43条1項)。
イ. 本件では、まず、被告(関東財務局長(4)第01265号)及び被告の前身であるディックファイナンス株式会社(近畿財務局長(1)第00671号)が「登録業者」である点につき、問題はない。
ウ. 次に、被告及び被告の前身であるディックファイナンス株式会社(以下、「ディック」という。)の極度額借入契約書兼告知書のサンプル(乙第4号証の1・2)には、貸主の名称(商号)、所在地、登録番号、契約年月日、契約番号、利率、返済方式、返済期間・回数、遅延損害金の割合、融資限度額等が記載され、また、領収証兼ご利用利用明細票のサンプル(乙第5号証の1・2)にも、上記極度額借入契約書兼告知書と同様の事項が記載されているので、被告及びディックが貸付を行う際に、旧貸金業規制法17条1項及び同施行規則13条に定める事項を記載した「17条書面を交付」していたことは明白である。
エ. 更に、上記ウで主張立証した通り、被告及びディックの領収証兼ご利用明細票のサンプル(乙第6号証の1・2)には、貸主の名称(商号)、所在地、登録番号、契約年月日、契約番号、利率、返済方式、返済期間・回数、遅延損害金の割合、融資限度額等が記載されているので、被告及びディックが弁済を受ける際に、旧貸金業規制法18条及び同施行規則15条に定める事項を記載した「18条書面を交付」していたことは明白である
オ. 最後に、「債務者が利息として任意に支払った」(貸金業法43条1項)とは、「債務者が利息の契約に基づく支払に充当されることを認識した上、自己の自由な意思によって支払ったことをいい、債務者において、その支払った金銭の額が利息の制限を越えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しないと解するのが相当である(最高裁昭和62年(オ)第1531号平成2年1月22日第二小法廷判決・民集44巻1号332頁参照。)。」とされるので、当事者間の合意に基づく原告の支払いは、強制執行、貸主等の威迫等(貸金業法21条)に起因するものでない限り、「任意の弁済」であることが明白である。
カ. 以上により、被告が貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有していたことは肯定できる。
(3)「特段の事情の有無」について
ア. 上記(2)で主張立証した通り、被告が、貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有していたことは肯定できるので、「そのような認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる特段の事情」が存在すれば「悪意の受益者」(民法704条)には該当しない。
イ. この点、被告では、みなし弁済の成否によって営業利益が大きく左右されるので、それが成立するためのシステム(みなし弁済システム)を長年にわたって構築・整備してきた。その結果、熊本地裁平成13年4月20日判決(同庁平成12年(レ)第25号)などでは、被控訴人(一審被告)のみなし弁済の抗弁が採用され、控訴人(一審原告)の控訴は棄却されている。
にもかかわらず、みなし弁済の成立が否定されるに至ったのは、みなし弁済の成立要件に関する解釈に変更が生じたことが原因であり、以下で詳細する通り、「被告の努力によっては如何ともしえない外部的な要因に起因」するものである。
ウ. 要件解釈の変遷
(ア)平成16年2月20日最高裁判決まで
当初は、任意性要件及び第17条・第18条書面要件について、いわゆる緩和説を採用する最高裁判決が存在し、当時の下級審判例及び学説も緩和説を採用するものが見られた。すなわち、最高裁平成2年1月22日判決(民集44巻1号332頁)は、みなし弁済における「任意」とは、債務者が利息の契約に基づく利息または賠償額の予定に基づく賠償金の支払いに充当されることを認識した上、自己の自由な意思によって支払ったことをいい、支払い金額が利息制限法の制限を超過していたことや、当該超過部分の契約が無効であることまでの認識は不要とし、任意性要件を緩やかに解していた。そして、この事件で、上告人は①契約年月日の記載が真実と異なる②借り換えの場合に記載すべき旧債務の金額が記載されていない と主張したが、最高裁はいずれも第17条書面の欠陥として取り上げず、みなし弁済を認めた。また、同判決の判例評釈(ジュリ959号92頁)において、当時最高裁調査官であった滝澤孝臣氏は、第17条及び第18条書面について、「契約書面及び受取証書の記載事項が法一七条及び一八条の所定事項、さらに大蔵省令の所定事項、銀行局長通達の所定事項のすべてを網羅していること、またその記載事項が事実と寸分違わず一致していることを要するというような杓子定規な解釈適用ではなく、事実に即した幅のある弾力的な解釈適用を肯認する趣旨に解される」と述べており、第17条・第18条書面要件についても、この当時、最高裁はいわゆる緩和説を採用していたものと考えられる。
その後の判例、学説等を見ても、さまざまな見解が錯綜し、統一が図られていなかった。確かに、第17条・第18条書面要件について、わずかな記載漏れも許されないとする下級審の裁判例も存在する一方、書面用件の不備ないし欠陥によって債務者が不利益を被るか否かを実質的に判断し、結果として要件を満たす旨判断した裁判例も複数存在し(東京高裁平成9年6月10日判決(判夕966号243頁)、最高裁平成11年3月11日判決(民集53巻3号451頁)、福岡地裁平成12年1月28日判決(金判1088号47頁)、名古屋高裁平成13年7月12日判決(判夕1126号280頁)、札幌高裁平成14年2月28日判決(金判1142号23頁)等)、また、第17条・第18条書面要件の解釈については、消費者金融の実務に照らして弾力的かつ緩やかな解釈を行うべきであるとする学説も有力に展開されていた(例えば、遠藤美光「貸金業規制法43条1項における書面の要件」ジュリ987号109頁、吉野正三郎「貸金業規制法17条の書面要件について」ジュリ1212号64号等)。
任意性要件についても、緩和説を採用した上記最高裁平成2年1月22日判決を前提に、期限の利益損失条項が含まれる金銭消費貸借契約に基づく制限超過利息の支払について、任意性を否定した判例は、ただの一つも存在しなかった。最近公表された前述の滝澤孝臣氏の論稿(銀行法務21・659号4頁)においても、同最高裁平成2年1月22日判決以降の状況に関して、「平成2年判決が言い渡されてから現在まで多数の貸金業取引関係訴訟が係属したなかで、かつ、貸金業取引のほとんどに期限の利益喪失約款が存在するのではないかと窺われるので、期限の利益喪失約款の下での利息ないし損害金の支払いの任意性といった法律問題は、みなし弁済規定の適否が争われる事案では、法律の適用として、裁判所で当然に問題となっていた事項であると解されるなかで、これまでに支払いの任意性が否定されるとの裁判例」がなかった旨述べられているところである(同13頁)、また、大蔵省の外郭団体が出版している解説書である「新訂実例問答集 貸金業法のすべて」(財団法人大蔵財務協会編 平成10年)においては、「任意」の意味について「一般に詐欺、錯誤、強迫が認められ、又は強制執行によって強制的に弁済にあてられた場合を除くものと解されており、規制法43条の『任意』もこれと変わることはないものと解される」とし(同220頁)、任意性が否定される場合を「詐欺」「錯誤」「強迫」「強制執行」といった例外的な場合に限定し、一般の意味にしたがって任意性を認める考えを示していた。
(イ)平成16年2月20日最高裁判決以降
しかし、最高裁は、平成16年2月20日判決において、「法43条1項の規定の適用要件については、これを厳格に解釈すべきもの」とし、第17条・第18条書面要件について、緩和説を捨て去り、厳格説を採用したようなことを述べるに至った。
他方、下級審においては混乱が続き、たとえば福岡高裁平成16年11月18日判決(平成16年(ネ)第488号、公刊物未搭載)は、「返済期間及び返済回数(貸金業法17条1項6頁)の記載を要しないと解すべきであるし、そのように解しても、債務者の保護に欠けることはないというべきである」として、いわゆるリボルビング取引についてみなし弁済の成立を認めた。
また、最高裁自身も、平成17年12月15日、厳格説に立ちつつも、その解釈に一定の幅を認める注目すべき判決を下している(消費者法ニュース・66号36頁)。すなわち、第17条書面の要件について、貸付契約の性質上、法定記載事項のうち、確定的な記載が不可能な事項があった場合、当該事項の記載の義務を免れるものではないとしつつも、当該事項に「準じた事項」を記載すれば、当該事項を記載したものと解すべき旨判示しているのである。つまり、最高裁も、厳格説に立ちつつも、貸金業者に不可能を強いることまでは否定し、契約の性質からして可能な限りの法定記載事項に「準じた記載」をすれば、第17条書面の要件を満たすものと認めているのである。これは第17条書面の要件を厳格に解釈しつつも絶対視せず、契約の性質に応じた被告の合理的な努力を評価するものといえる。したがって、厳格説といっても、それは全ての場合において、第17条・第18条書面要件として法文上定められている事項が厳格に一言一句反映されていることまでを要求するものではなく、契約の性質に応じた柔軟な解釈の余地を残すものというべきである。
さらに、任意性要件については、前記の最高裁平成16年2月20日判決は直接判示しておらず、その後の東京高裁平成16年12月21日判決(金判1208号13頁)においては、緩和説を採用する従前の最高裁平成2年1月22日判決を前提に、期限の利益損失特約の存在によって直ちに制限超過利息の支払が強制されることはないとし、前述した滝澤孝臣判事も同東京高裁判決を支持していた(金判1231号11頁)。
(ウ)平成18年1月13日最高裁判決以降
ところが、最高裁は、その後厳格な立場を強め、平成18年1月13日判決において、第18条書面の記載事項の一部省略を認める貸金業規制法施行規則第15条2項の規定の一部を無効とし、さらに、同判決、同月19日判決(裁時1404号71頁)及び同月24日判決(裁時1404号89頁)において、金銭消費貸借に制限超過利息の支払を遅滞した場合の期限の利益損失条項がある場合には、特段の事情がない限り、支払いの任意性が否定されるとの判断を下したことは周知のとおりである。
エ. 結論
以上のとおり、みなし弁済の成立が否定されるに至ったのは「みなし弁済の成立要件に関する解釈に変更が生じたことが原因であり、被告の努力によっては如何ともしえない外部的な要因に起因」するものである。
そして、上記事情に加えて、「通説は現実に知る者だけが悪意の受益者であり、善意であれば、過失の有無を問わず、前条の責任のみを負うものとする。」(「新版注釈法(18)」、640頁)と理解していること、及び「ある利得が将来法律上の原因を欠くものとなる可能性を知る場合については、・・・一般的には、そのような場合は必ずしも悪意の受益者とはいえない。」(「新版注釈法(18)」、641頁)と解されていることに鑑みれば、本件には、「みなし弁済が成立するとの認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる特段の事情」が存在するので、被告は、「悪意の受益者」(民法704条)には該当しない。
4、総括
以上の被告の主張を総括すれば、そもそも被告は「悪意の受益者」(民法704条)に該当しないので、過払利息(年5分)の返還義務を負わないし、仮に、「悪意の受益者」(民法704条)に該当する場合でも、過払金の不当利得返還請求権の金額や内容は、継続的な金銭消費貸借取引終了日以降に確定するものであって、当該時点までは金額や内容が不確定、不動的であるから、過払金の不当利得返還請求権の金額や内容、その権利が確定した日、すなわち、原告の当該返還請求権の行使により被告がその訴状を受領した日の翌日までは、過払利息(年5分)の返還義務を負わないもとの解する。
5、本件で被告が原告に負う不当利得返還債務の金額
上記主張にて、被告が原告に負う不当利得返還債務は、以下の金額を越えて存在しない。
・本件取引 金66,897円(被告別紙計算書)
第3.和解提案
(1)はじめに
被告は、原告との本件争いについて和解による解決を希望しており、被告は答弁書にて6万円の和解案を提示したが、原告は「印紙1,000円、郵券4,000円、資格証明1,000円、訴状作成費用1,000円及び、支払日迄5%でないと和解しない」と判決と同様の内容であった為、合意に至っておりません。
和解とは、『当事者間に存在する法律関係の争いについて、当事者が互いに譲歩し、争いを止める合意をすることをいう。和解契約が成立するためには、以下の要件を満たすことが必要である(民法695条)。①当事者間に争いが存在すること、②当事者が互いに譲歩すること、③争いを解決する合意をすること(出典:フリー百科事典ウィキペディア(Wikipedia))。』である。
被告は、本件について早期の解決を希望するものであり、当事者が互いに譲歩し、和解に応じて頂けたらと思います。
原告におかれましては、このあたりを勘案して和解に応じて頂きたいと願います。もしくは、裁判所による和解勧告の実施を希望いたします。
(2)和解案
被告は、原告との本件争いについて和解による解決を希望する。答弁書にて6万円の和解案を提示したが、原告との間で和解が成立しなかったため、改めて本件係争に関して和解案を提示する。被告は、原告に対し、本件解決金として金75,000円を上限に、5月22日を支払日として支払う用意がある。
第4.被告の主張・要望
1.被告は、続行期日に欠席した場合、本書面の内容を擬制陳述いたします。
2.被告は、本件訴訟の速やかな解決のため、和解勧告を出して欲しい為、上申いたします。
↑↑↑↑↑↑ ここまで 被告の準備書面(1) ↑↑↑↑↑↑
CFJ訴訟 被告の準備書面(1)関連エントリー
| ■■■■■ お知らせ ■■■■■ |
|---|
|
当サイトは、 「過払い金ゲットブログ~本人訴訟で過払金請求~」 ( http://kabaraiget.seesaa.net/ ) をHTMLファイルに、移植・変換したものです。 リンクについては、移植の際、チェックしていますが、チェック漏れがある可能性もありますので、その時はご容赦下さい。 最新情報については、上記ブログでご確認ください。 |