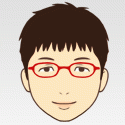大阪高裁平成20年4月18日控訴審判決
これは「取引終了までの過払金は発生しない」とした
大阪高裁の平成20年4月18日判決をタイプしたものです。
判決をネットで調べたのですが、分からなかったので、
参考文献として、自分で打ち直したものです。
誤字や判決のリンクがあれば、教えていただけると助かります。
CFJは、当判決と山口地裁平成21年2月25日判決
において、「取引終了までの過払利息は発生しない」
との判決が出たと主張しています。
また、 控訴審の場合、原審がないと理解するのに苦労しますので、
原審である京都地方裁判所平成19年(ワ)第1456号については、
現在調査中です。
↓↓↓↓↓↓ ここから 判決 ↓↓↓↓↓↓
平成20年4月18日判決言渡
平成19年(ネ)第3343号 不当利得返還請求控訴事件
(原審・京都地方裁判所平成19年(ワ)第1456号)
判 決
控訴人(1審原告) 一般の方
代理人 弁護士
被控訴人(1審被告) プロミス株式会社
主 文
1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人は,控訴人に対し,185万6024円及びこれに対する平成9年8月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 控訴人のその余の請求を棄却する。
2 控訴費用は,第1,第2審を通じ,これを4分し,その1を控訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。
3 この判決の主文第1項(1)は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は,控訴人に対し,229万4826円並びに,うち185万6024円に対する平成9年8月30日から,うち18万円に対する平成19年6月5日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 控訴費用は,第1,第2審とも被控訴人の負担とする。
4 仮執行宣言
第2 事実の概要
1 事実の要旨
本件は,控訴人が貸金業者である被控訴人に対し,控訴人は,昭和60年8月23日から平成9年8月29日まで,被控訴人との間で,継続的に金銭の借入れと弁済を繰り返してきたところ,その一連の取引について利息制限法に基づいて充当計算すると185万6024円の過払金が生じているとして,①不当利得返還請求権に基づき,上記過払金185万6024円,平成9年8月29日までの法定利息25万8802円,及び,上記185万6024円に対する同月30日から支払い済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払を求めるとともに,②民法704条後段に基づき,弁護士費用18万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成19年6月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
原判決は,控訴人の請求を一部認容し,控訴人が上記請求の全部認容を求めて本件控訴を提起したものである。
2 前提となる事案は,原判決第二,二(2頁15行目から3頁5行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
3 争点及びこれに関する当事者の主張は,次のとおり,当審における主張を付加するほかは,原判決第二,三及び四(3頁6行目から5頁22行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
【控訴人の当審における主張】
(1)争点2(時効の起算点)について
ア 本件では,昭和60年8月23日ころに極度額を50万円とする包括的金銭消費貸借契約が締結され,その後,昭和62年11月10日ころに極度額が70万円に増額され,これに基づき,控訴人は,被控訴人から昭和60年8月23日以降,平成9年8月29日までの間,借入と返済を繰り返していた(甲1)。
イ このような基本契約に基づく1個の連続した貸付取引においては,借入金債務に対する各弁済は,各貸付毎に個別的な対応関係をもって行われることが予定されているものではなく,基本契約に基づく借入金全体に対して行われるものであって,充当の対象となるのはこのような全体としての借入金債務であると解される。このような基本契約に基づく1個の連続した貸付取引においては,当事者は一つの貸付を行う際に,次の個別の貸付を行うことを想定しているのであり,複数の権利関係が発生するような事態が生ずることを望まないのが通常であることを照らしても制限超過部分を元本に充当した結果,過払金が発生した場合には,その後の発生する新たな借入金債務に充当することを合意しているものと解される(最高裁平成19年6月7日第一小法廷判決・民法61巻4号1537頁,最高裁平成19年7月19日第一小法廷判決・判例時報1981号15頁)。
ウ 本件の場合,本件各貸付は,1個の連続した貸付取引であり,この基本契約に基づく債務の弁済は,各貸付毎に個別的な対応関係をもって行われることが予定されているものではなく,基本契約に基づく借入金全体に対して行われ,充当の対象となるのも全体としての借入金債務であると認めるべきである。
そして,基本契約に基づく借入金債務に対する各弁済金のうち,制限超過部分を元本に充当した結果,過払金が発生した場合には,当該過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと認められる。
また,本件は,基本契約に基づき,限度額を定めて継続的に借入と返済を繰り返したものであり,実質的に一連の貸付であり,控訴人と被控訴人が,一つの貸付を行う際に次の個別の貸付けを行うことを想定しており,複数の権利関係が発生するような事態が生ずることを望まないのが通常であることに照らしても,制限超過部分を元本に充当した結果,過払金が発生した場合には,その後に発生する新たな借入金債務に充当することを合意しているということができる。
したがって,本件において,過払金の不当利得返還請求権の金額が確定し,消滅時効が進行するのは,1個の連続した貸付取引の終了時,すなわち,平成9年8月29日であると解するのが相当である。
エ ある時点において計算される過払金について,10年以上前の弁済によって生じた部分とそうでない部分とを計算によって区分することは不可能ではないが,1個の過払金返還請求権を人為的に区分し,前者は消滅時効によって消滅しており,後者だけが現存していると論じることは,通常,借主である控訴人の側で取引継続中に過払金が発生していると認識することが極めて困難であって,事実上不可能を強いることになること,加えて,過払金が発生している事実を貸主である控訴人に告げず,むしろ,違法な高金利を徴収し続けた被控訴人に資する判断となることから考えれば,妥当ではない。
オ 控訴人が計算上,過払金の発生の都度遅延損害金を付加しているのは,取引終了時に,被控訴人に対する過払金返還債権の金額を確定するために行う作業において,控訴人と被控訴人の公平を図るために各弁済により生じる過払金に利息を付加しているだけのことであり,遅延損害金を付加して計算しているからといって,個々の不当利得返還請求権であることを認識しているわけではない。
(2)争点4(民法704条後段に基づく弁護士費用の請求の可否及びその額)について
ア 民法704条後段は,悪意の受益者が利得を返還しても損失者のもとに不当利得の原因たる事実から生じた損害であって,なお補填されないで残る損害を補填せよという規定であり,不当利得制度を支える公平の原理を貫くために認められたものであるから,不当利得返還請求権の性質を有する。よって,不法行為が成立する場合の損害賠償義務を定めたものではない。
イ 本件の場合,控訴人が弁護士に依頼して返還請求を行わない限り,被控訴人が任意に過払金を返還することは全く考えられず,被控訴人には積極的に取引履歴を開示するなどして債権債務を清算すべき義務は存在しないことからして,弁護士費用は民法704条後段の損害に該当する。
ウ 仮に,不法行為の要件を問題とするとしても,貸金業者が利息制限法1条1項の法定金利を超過する利息を徴収する行為は,強行法規である利息制限法に違反する行為であって,不法行為である。貸金業法43条1項は,このような行為について,一定の厳格な要件を満たした場合のみ,違法状態を解消して当該制限超過利息の約定を有効とし,もって,制限超過利息の徴収を正当化する規定にすぎないから,本件のように,貸金業法43条1項の適用の余地が全くない事案においては,何ら被控訴人による制限超過利息の徴収が正当化されるものではなく,原則として被控訴人には不法行為が成立する。
【被控訴人の当審における主張】
(1)争点2(時効の起算点)について
ア 過払金は,利息制限法上限利率を超過する約定利息を元本に充当した結果,元本が計算上零になって以降,支払った各弁済が不当利得となるから,本件で控訴人が請求している権利は,単一の権利ではなく,個々の不当利得返還請求権集積した結果である。
イ 控訴人は,過払金が発生する都度,民法704条所定の遅延損害金を付加している。利息が吹かされる人は,悪意の受益者を利益を受けた日,すなわち,不当利得返還請求権の発生日であるから,控訴人の主張するように最終取引日から不当利得返還請求権の消滅時効期間が起算されるのならば,遅延損害金が付加される日も最終取引日でなければならない。そして,当該不当利得返還請求権は単一の権利でなければならない。
ところが,控訴人は,本件において各返済ごとに遅延損害金を付加しているから,消滅時効の起算日の主張とは裏腹に,自身が請求しているのは個々の不当利得返還請求権であると認識しているものと考えられる。
(2)争点4(民法704条後段に基づく弁護士費用の請求の可否及びその額)について
ア 民法704条後段の責任の性質
民法704条後段は,不法行為責任を注意的に規定したものと解すべきである。
この点,法定特別責任説もあるが,賠償すべき損害の範囲については,民法416条を基本とした損害賠償制度に回帰せざるを得ないという論理的解釈がある。そして,本件で,信頼利益を問題とするならば,控訴人の主張する弁護士費用は射程外となってしまう。
イ 不法行為の成否
債務者と貸金業者との取引関係の清算は,詐欺的な架空請求とは全く側面を異にしており,被控訴人に不法行為責任が成立するためには,要件事実として,故意過失が必要であるところ,本件において控訴人・被控訴人間の取引を利息制限法に引き直して計算すると過払金が発生するとしても,直ちに故意過失が認められるわけではない。利息制限法1条2項は、任意に支払った利息制限法所定の上限利率を超えた利息を返還しなくてよい旨を同時に定めており,貸金業者は貸金業法43条の各要件事実を満たせば過払金の給付保持力を得ることになる。大多数の債務者は,約定利息を返済し,存在的に「みなし利息」を肯定・許容していることを考えると,被控訴人に不法行為責任が成立するためには,被控訴人が,利息制限法に引き直して計算すると過払金が発生することを認識しているだけでは足りず,これに加えて,控訴人が将来過払金返還請求訴訟や債務整理を行い,みなし利息を認める意思がないということを確定的に認識していなければならない。
第3 当裁判所の判断
1 争点1(被控訴人の悪意)について
(1)原判決第三,一(5頁24行目から6頁4行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
(2)前記前提となる事実によれば,控訴人と被控訴人は,昭和60年8月23日,極度借入基本契約を締結し,控訴人は,昭和60年8月23日から平成9年8月29日まで,被控訴人から,原判決別紙1「計算書」の「年月日」欄記載の日に,「借入金額」欄記載の金額を借り入れ,「弁済額」欄記載の金額を弁済したものである。
これによれば,控訴人は,随時6000円ないし50万円を借り入れており,当初の50万円の借入に対し,返済未了の間に,新たに18万円の借入がされるなど,以後,返済未了の間に新たな借入が繰りかえられていたこと,返済については,控訴人は,毎月,20日ないし末日までに返済をしているところ,返済額は,取引当初から平成5年末までは,2万円,2万5000円又は3万円が多く,平成6年1月以降は1万円,1万5000円又は2万円が多くなっていたことが認められる。このような借入と返済の経緯からすると,借入額と返済額の対応関係は認められず,累積された借入額全体に対し,返済が行われていると認められる。平成4年4月27日を最後として,新たな借入は行われていないが,これは,借入残高が極度額(その額は,当初の借入額が50万円であり,その後,相当額の返済後に,再び借入が繰り返されていることや,最終の返済額が41万余円であることなどから,50万円と推定される。)を超過していたことによるとも考えられる。したがって,当初契約に基づき計算した元利金を完済した取引終了時といえる平成9年8月29日以降は新たな借入や返済がされることがなくなったといえるものの,それまでの間は,新たな借入や返済の行われる可能性がなかったとはいえない。
そうすると,本件各貸付は,基本契約に基づく連続した貸付取引であり,債務の弁済は,各貸付毎に個別的な対応関係をもって行われることが予定されているものではなく,基本契約に基づく借入金全体に対して行われ,充当の対象となるのも全体としての借入金債務であると認められるから,控訴人と被控訴人は,一つの貸付を行う際に次の個別の貸付を行うことが想定される契約関係にあることを前提に,複数の権利関係が発生するような事態の生ずることを望まなかったものといえ,制限超過部分を元本に充当した結果,過払金が発生した場合には,その後に発生する新たな借入金債務に充当することを合意していたと認められる。
したがって,本件において,過払金の不当利得返還請求権の金額や内容は,後の貸付の充当が行われたいこととなる取引最終日以降に確定するのであり、当該時点までは金額や内容が不確定,浮動的であって,後の貸付への充当の有無,充当額等により変動することが予想されるから,利得の金額や内容も不確定,不動的であり,これにつき利息を付して返還させることは,当該利息の金額や内容自体不確定,不動的である上,不当利得制度を支える公平の原理をも考慮すると,不相当である。
本件において,上記最終完済日より前に取引が終了したといえないことは明らかであるから,控訴人主張の各日時をもって,上記利息を付することのできる開始時点とすることはできず,上記最終完済日以降,新たな借入や返済がされることがなくなり過払金の不当利得返還請求権の金額や内容が確定して取引が終了したということができ,当該時点からの利息を付した返還を認めることができる。
控訴人の不当利息返還請求権は,原判決別紙1の計算書のとおり,最終完済日現在の過払金額185万6024円及びこれに対する平成9年8月30日から民法所定の約定利息(年5分)の支払を求める限度において認められる。
2 争点2(時効の起算点)について
上記のとおり,本件各貸付は,基本契約に基づく連続した貸付取引であり,債務の弁済は,各貸付毎に個別的な対応関係をもって行われることが予定されているものではなく,基本契約に基づく借入金全体に対して行われ,充当の対象となるのも全体としての借入金債務であると認められ,過払金の不当利得返還請求権の金額や内容は,後の貸付への充当が行われないこととなる取引の終了時以降に確定するのであり,当該時点から当該請求権を行使得ることとなるから,同時点から消滅時効期間が進行するというのが相当であり,本件において,、上記最終完済日平成9年8月29日より前に取引が終了したといえないことは明らかであって,被控訴人主張の日時をもって,消滅時効期間の開始時点とすることはできず,本件訴え提起のされた平成19年5月18日までの間に消滅時効が完成したといえないから,被控訴人の消滅時効の抗弁は認められない。
3 争点4(民法704条後段に基づく弁護士費用の請求の可否及びその額)について
次のとおり付加するほか,原判決第三,四(8頁16行目から9頁9行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 民法704条後段は,不法行為が成立する場合の損害賠償義務を注意的に規定したものと解すべきである。悪意の利得者は,公平の見地から,利得に利息を付加して返還しなければならないとされるが,なお損害の賠償の責任を負うのは,故意又は過失に基づき損害を与えた場合,すなわち,不法行為の要件を備えたときとするのが公平の見地からすると妥当と考えられるからである。
(2) 最高裁平成16年(受)第965号同17年7月19日第三小法廷判決・民集59巻6号1783頁は,貸金業者が,債務者から取引履歴の開示を求められた場合に保存している業務帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を認めたものにすぎず,貸金業者が債務者から開示を求められてもいないのに,積極的にその取引を開示するなどして,債権債務を清算すべき義務を認めたものではない。
4 結論
よって,控訴人の請求は,185万6024円及びこれに対する平成9年8月30日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で認容し,その余を棄却すべきであり,原判決を上記のとおり変更し,主文のとおり判決する。
(当審口頭弁論最終日 平成20年2月29日)
大阪高等裁判所第8民事部
裁判長 裁判官 ○○ ○○
裁判官 ○○ ○○
裁判官○○ ○○は,転官のため,署名,捺印できない。
裁判長 裁判官 ○○ ○○
↑↑↑↑↑↑ ここまで 判決 ↑↑↑↑↑↑
大阪高裁の平成20年4月18日判決をタイプしたものです。
判決をネットで調べたのですが、分からなかったので、
参考文献として、自分で打ち直したものです。
誤字や判決のリンクがあれば、教えていただけると助かります。
CFJは、当判決と山口地裁平成21年2月25日判決
において、「取引終了までの過払利息は発生しない」
との判決が出たと主張しています。
また、 控訴審の場合、原審がないと理解するのに苦労しますので、
原審である京都地方裁判所平成19年(ワ)第1456号については、
現在調査中です。
↓↓↓↓↓↓ ここから 判決 ↓↓↓↓↓↓
平成20年4月18日判決言渡
平成19年(ネ)第3343号 不当利得返還請求控訴事件
(原審・京都地方裁判所平成19年(ワ)第1456号)
判 決
控訴人(1審原告) 一般の方
代理人 弁護士
被控訴人(1審被告) プロミス株式会社
主 文
1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人は,控訴人に対し,185万6024円及びこれに対する平成9年8月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 控訴人のその余の請求を棄却する。
2 控訴費用は,第1,第2審を通じ,これを4分し,その1を控訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。
3 この判決の主文第1項(1)は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は,控訴人に対し,229万4826円並びに,うち185万6024円に対する平成9年8月30日から,うち18万円に対する平成19年6月5日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 控訴費用は,第1,第2審とも被控訴人の負担とする。
4 仮執行宣言
第2 事実の概要
1 事実の要旨
本件は,控訴人が貸金業者である被控訴人に対し,控訴人は,昭和60年8月23日から平成9年8月29日まで,被控訴人との間で,継続的に金銭の借入れと弁済を繰り返してきたところ,その一連の取引について利息制限法に基づいて充当計算すると185万6024円の過払金が生じているとして,①不当利得返還請求権に基づき,上記過払金185万6024円,平成9年8月29日までの法定利息25万8802円,及び,上記185万6024円に対する同月30日から支払い済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払を求めるとともに,②民法704条後段に基づき,弁護士費用18万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成19年6月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
原判決は,控訴人の請求を一部認容し,控訴人が上記請求の全部認容を求めて本件控訴を提起したものである。
2 前提となる事案は,原判決第二,二(2頁15行目から3頁5行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
3 争点及びこれに関する当事者の主張は,次のとおり,当審における主張を付加するほかは,原判決第二,三及び四(3頁6行目から5頁22行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
【控訴人の当審における主張】
(1)争点2(時効の起算点)について
ア 本件では,昭和60年8月23日ころに極度額を50万円とする包括的金銭消費貸借契約が締結され,その後,昭和62年11月10日ころに極度額が70万円に増額され,これに基づき,控訴人は,被控訴人から昭和60年8月23日以降,平成9年8月29日までの間,借入と返済を繰り返していた(甲1)。
イ このような基本契約に基づく1個の連続した貸付取引においては,借入金債務に対する各弁済は,各貸付毎に個別的な対応関係をもって行われることが予定されているものではなく,基本契約に基づく借入金全体に対して行われるものであって,充当の対象となるのはこのような全体としての借入金債務であると解される。このような基本契約に基づく1個の連続した貸付取引においては,当事者は一つの貸付を行う際に,次の個別の貸付を行うことを想定しているのであり,複数の権利関係が発生するような事態が生ずることを望まないのが通常であることを照らしても制限超過部分を元本に充当した結果,過払金が発生した場合には,その後の発生する新たな借入金債務に充当することを合意しているものと解される(最高裁平成19年6月7日第一小法廷判決・民法61巻4号1537頁,最高裁平成19年7月19日第一小法廷判決・判例時報1981号15頁)。
ウ 本件の場合,本件各貸付は,1個の連続した貸付取引であり,この基本契約に基づく債務の弁済は,各貸付毎に個別的な対応関係をもって行われることが予定されているものではなく,基本契約に基づく借入金全体に対して行われ,充当の対象となるのも全体としての借入金債務であると認めるべきである。
そして,基本契約に基づく借入金債務に対する各弁済金のうち,制限超過部分を元本に充当した結果,過払金が発生した場合には,当該過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと認められる。
また,本件は,基本契約に基づき,限度額を定めて継続的に借入と返済を繰り返したものであり,実質的に一連の貸付であり,控訴人と被控訴人が,一つの貸付を行う際に次の個別の貸付けを行うことを想定しており,複数の権利関係が発生するような事態が生ずることを望まないのが通常であることに照らしても,制限超過部分を元本に充当した結果,過払金が発生した場合には,その後に発生する新たな借入金債務に充当することを合意しているということができる。
したがって,本件において,過払金の不当利得返還請求権の金額が確定し,消滅時効が進行するのは,1個の連続した貸付取引の終了時,すなわち,平成9年8月29日であると解するのが相当である。
エ ある時点において計算される過払金について,10年以上前の弁済によって生じた部分とそうでない部分とを計算によって区分することは不可能ではないが,1個の過払金返還請求権を人為的に区分し,前者は消滅時効によって消滅しており,後者だけが現存していると論じることは,通常,借主である控訴人の側で取引継続中に過払金が発生していると認識することが極めて困難であって,事実上不可能を強いることになること,加えて,過払金が発生している事実を貸主である控訴人に告げず,むしろ,違法な高金利を徴収し続けた被控訴人に資する判断となることから考えれば,妥当ではない。
オ 控訴人が計算上,過払金の発生の都度遅延損害金を付加しているのは,取引終了時に,被控訴人に対する過払金返還債権の金額を確定するために行う作業において,控訴人と被控訴人の公平を図るために各弁済により生じる過払金に利息を付加しているだけのことであり,遅延損害金を付加して計算しているからといって,個々の不当利得返還請求権であることを認識しているわけではない。
(2)争点4(民法704条後段に基づく弁護士費用の請求の可否及びその額)について
ア 民法704条後段は,悪意の受益者が利得を返還しても損失者のもとに不当利得の原因たる事実から生じた損害であって,なお補填されないで残る損害を補填せよという規定であり,不当利得制度を支える公平の原理を貫くために認められたものであるから,不当利得返還請求権の性質を有する。よって,不法行為が成立する場合の損害賠償義務を定めたものではない。
イ 本件の場合,控訴人が弁護士に依頼して返還請求を行わない限り,被控訴人が任意に過払金を返還することは全く考えられず,被控訴人には積極的に取引履歴を開示するなどして債権債務を清算すべき義務は存在しないことからして,弁護士費用は民法704条後段の損害に該当する。
ウ 仮に,不法行為の要件を問題とするとしても,貸金業者が利息制限法1条1項の法定金利を超過する利息を徴収する行為は,強行法規である利息制限法に違反する行為であって,不法行為である。貸金業法43条1項は,このような行為について,一定の厳格な要件を満たした場合のみ,違法状態を解消して当該制限超過利息の約定を有効とし,もって,制限超過利息の徴収を正当化する規定にすぎないから,本件のように,貸金業法43条1項の適用の余地が全くない事案においては,何ら被控訴人による制限超過利息の徴収が正当化されるものではなく,原則として被控訴人には不法行為が成立する。
【被控訴人の当審における主張】
(1)争点2(時効の起算点)について
ア 過払金は,利息制限法上限利率を超過する約定利息を元本に充当した結果,元本が計算上零になって以降,支払った各弁済が不当利得となるから,本件で控訴人が請求している権利は,単一の権利ではなく,個々の不当利得返還請求権集積した結果である。
イ 控訴人は,過払金が発生する都度,民法704条所定の遅延損害金を付加している。利息が吹かされる人は,悪意の受益者を利益を受けた日,すなわち,不当利得返還請求権の発生日であるから,控訴人の主張するように最終取引日から不当利得返還請求権の消滅時効期間が起算されるのならば,遅延損害金が付加される日も最終取引日でなければならない。そして,当該不当利得返還請求権は単一の権利でなければならない。
ところが,控訴人は,本件において各返済ごとに遅延損害金を付加しているから,消滅時効の起算日の主張とは裏腹に,自身が請求しているのは個々の不当利得返還請求権であると認識しているものと考えられる。
(2)争点4(民法704条後段に基づく弁護士費用の請求の可否及びその額)について
ア 民法704条後段の責任の性質
民法704条後段は,不法行為責任を注意的に規定したものと解すべきである。
この点,法定特別責任説もあるが,賠償すべき損害の範囲については,民法416条を基本とした損害賠償制度に回帰せざるを得ないという論理的解釈がある。そして,本件で,信頼利益を問題とするならば,控訴人の主張する弁護士費用は射程外となってしまう。
イ 不法行為の成否
債務者と貸金業者との取引関係の清算は,詐欺的な架空請求とは全く側面を異にしており,被控訴人に不法行為責任が成立するためには,要件事実として,故意過失が必要であるところ,本件において控訴人・被控訴人間の取引を利息制限法に引き直して計算すると過払金が発生するとしても,直ちに故意過失が認められるわけではない。利息制限法1条2項は、任意に支払った利息制限法所定の上限利率を超えた利息を返還しなくてよい旨を同時に定めており,貸金業者は貸金業法43条の各要件事実を満たせば過払金の給付保持力を得ることになる。大多数の債務者は,約定利息を返済し,存在的に「みなし利息」を肯定・許容していることを考えると,被控訴人に不法行為責任が成立するためには,被控訴人が,利息制限法に引き直して計算すると過払金が発生することを認識しているだけでは足りず,これに加えて,控訴人が将来過払金返還請求訴訟や債務整理を行い,みなし利息を認める意思がないということを確定的に認識していなければならない。
第3 当裁判所の判断
1 争点1(被控訴人の悪意)について
(1)原判決第三,一(5頁24行目から6頁4行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
(2)前記前提となる事実によれば,控訴人と被控訴人は,昭和60年8月23日,極度借入基本契約を締結し,控訴人は,昭和60年8月23日から平成9年8月29日まで,被控訴人から,原判決別紙1「計算書」の「年月日」欄記載の日に,「借入金額」欄記載の金額を借り入れ,「弁済額」欄記載の金額を弁済したものである。
これによれば,控訴人は,随時6000円ないし50万円を借り入れており,当初の50万円の借入に対し,返済未了の間に,新たに18万円の借入がされるなど,以後,返済未了の間に新たな借入が繰りかえられていたこと,返済については,控訴人は,毎月,20日ないし末日までに返済をしているところ,返済額は,取引当初から平成5年末までは,2万円,2万5000円又は3万円が多く,平成6年1月以降は1万円,1万5000円又は2万円が多くなっていたことが認められる。このような借入と返済の経緯からすると,借入額と返済額の対応関係は認められず,累積された借入額全体に対し,返済が行われていると認められる。平成4年4月27日を最後として,新たな借入は行われていないが,これは,借入残高が極度額(その額は,当初の借入額が50万円であり,その後,相当額の返済後に,再び借入が繰り返されていることや,最終の返済額が41万余円であることなどから,50万円と推定される。)を超過していたことによるとも考えられる。したがって,当初契約に基づき計算した元利金を完済した取引終了時といえる平成9年8月29日以降は新たな借入や返済がされることがなくなったといえるものの,それまでの間は,新たな借入や返済の行われる可能性がなかったとはいえない。
そうすると,本件各貸付は,基本契約に基づく連続した貸付取引であり,債務の弁済は,各貸付毎に個別的な対応関係をもって行われることが予定されているものではなく,基本契約に基づく借入金全体に対して行われ,充当の対象となるのも全体としての借入金債務であると認められるから,控訴人と被控訴人は,一つの貸付を行う際に次の個別の貸付を行うことが想定される契約関係にあることを前提に,複数の権利関係が発生するような事態の生ずることを望まなかったものといえ,制限超過部分を元本に充当した結果,過払金が発生した場合には,その後に発生する新たな借入金債務に充当することを合意していたと認められる。
したがって,本件において,過払金の不当利得返還請求権の金額や内容は,後の貸付の充当が行われたいこととなる取引最終日以降に確定するのであり、当該時点までは金額や内容が不確定,浮動的であって,後の貸付への充当の有無,充当額等により変動することが予想されるから,利得の金額や内容も不確定,不動的であり,これにつき利息を付して返還させることは,当該利息の金額や内容自体不確定,不動的である上,不当利得制度を支える公平の原理をも考慮すると,不相当である。
本件において,上記最終完済日より前に取引が終了したといえないことは明らかであるから,控訴人主張の各日時をもって,上記利息を付することのできる開始時点とすることはできず,上記最終完済日以降,新たな借入や返済がされることがなくなり過払金の不当利得返還請求権の金額や内容が確定して取引が終了したということができ,当該時点からの利息を付した返還を認めることができる。
控訴人の不当利息返還請求権は,原判決別紙1の計算書のとおり,最終完済日現在の過払金額185万6024円及びこれに対する平成9年8月30日から民法所定の約定利息(年5分)の支払を求める限度において認められる。
2 争点2(時効の起算点)について
上記のとおり,本件各貸付は,基本契約に基づく連続した貸付取引であり,債務の弁済は,各貸付毎に個別的な対応関係をもって行われることが予定されているものではなく,基本契約に基づく借入金全体に対して行われ,充当の対象となるのも全体としての借入金債務であると認められ,過払金の不当利得返還請求権の金額や内容は,後の貸付への充当が行われないこととなる取引の終了時以降に確定するのであり,当該時点から当該請求権を行使得ることとなるから,同時点から消滅時効期間が進行するというのが相当であり,本件において,、上記最終完済日平成9年8月29日より前に取引が終了したといえないことは明らかであって,被控訴人主張の日時をもって,消滅時効期間の開始時点とすることはできず,本件訴え提起のされた平成19年5月18日までの間に消滅時効が完成したといえないから,被控訴人の消滅時効の抗弁は認められない。
3 争点4(民法704条後段に基づく弁護士費用の請求の可否及びその額)について
次のとおり付加するほか,原判決第三,四(8頁16行目から9頁9行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 民法704条後段は,不法行為が成立する場合の損害賠償義務を注意的に規定したものと解すべきである。悪意の利得者は,公平の見地から,利得に利息を付加して返還しなければならないとされるが,なお損害の賠償の責任を負うのは,故意又は過失に基づき損害を与えた場合,すなわち,不法行為の要件を備えたときとするのが公平の見地からすると妥当と考えられるからである。
(2) 最高裁平成16年(受)第965号同17年7月19日第三小法廷判決・民集59巻6号1783頁は,貸金業者が,債務者から取引履歴の開示を求められた場合に保存している業務帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を認めたものにすぎず,貸金業者が債務者から開示を求められてもいないのに,積極的にその取引を開示するなどして,債権債務を清算すべき義務を認めたものではない。
4 結論
よって,控訴人の請求は,185万6024円及びこれに対する平成9年8月30日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で認容し,その余を棄却すべきであり,原判決を上記のとおり変更し,主文のとおり判決する。
(当審口頭弁論最終日 平成20年2月29日)
大阪高等裁判所第8民事部
裁判長 裁判官 ○○ ○○
裁判官 ○○ ○○
裁判官○○ ○○は,転官のため,署名,捺印できない。
裁判長 裁判官 ○○ ○○
↑↑↑↑↑↑ ここまで 判決 ↑↑↑↑↑↑
| ■■■■■ お知らせ ■■■■■ |
|---|
|
当サイトは、 「過払い金ゲットブログ~本人訴訟で過払金請求~」 ( http://kabaraiget.seesaa.net/ ) をHTMLファイルに、移植・変換したものです。 リンクについては、移植の際、チェックしていますが、チェック漏れがある可能性もありますので、その時はご容赦下さい。 最新情報については、上記ブログでご確認ください。 |